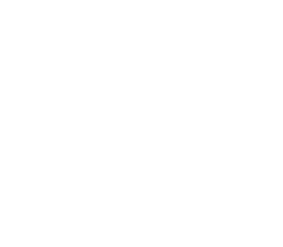
葬儀・告別式
葬儀は遺族・親族が故人のご冥福を祈る儀式であり、告別式は故人の友人、知人、所属の団体、ご近所の方など一般の参列者が故人とお別れをする儀礼です。
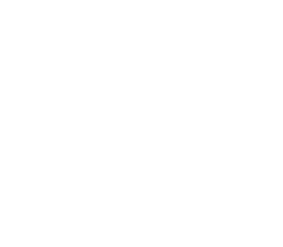
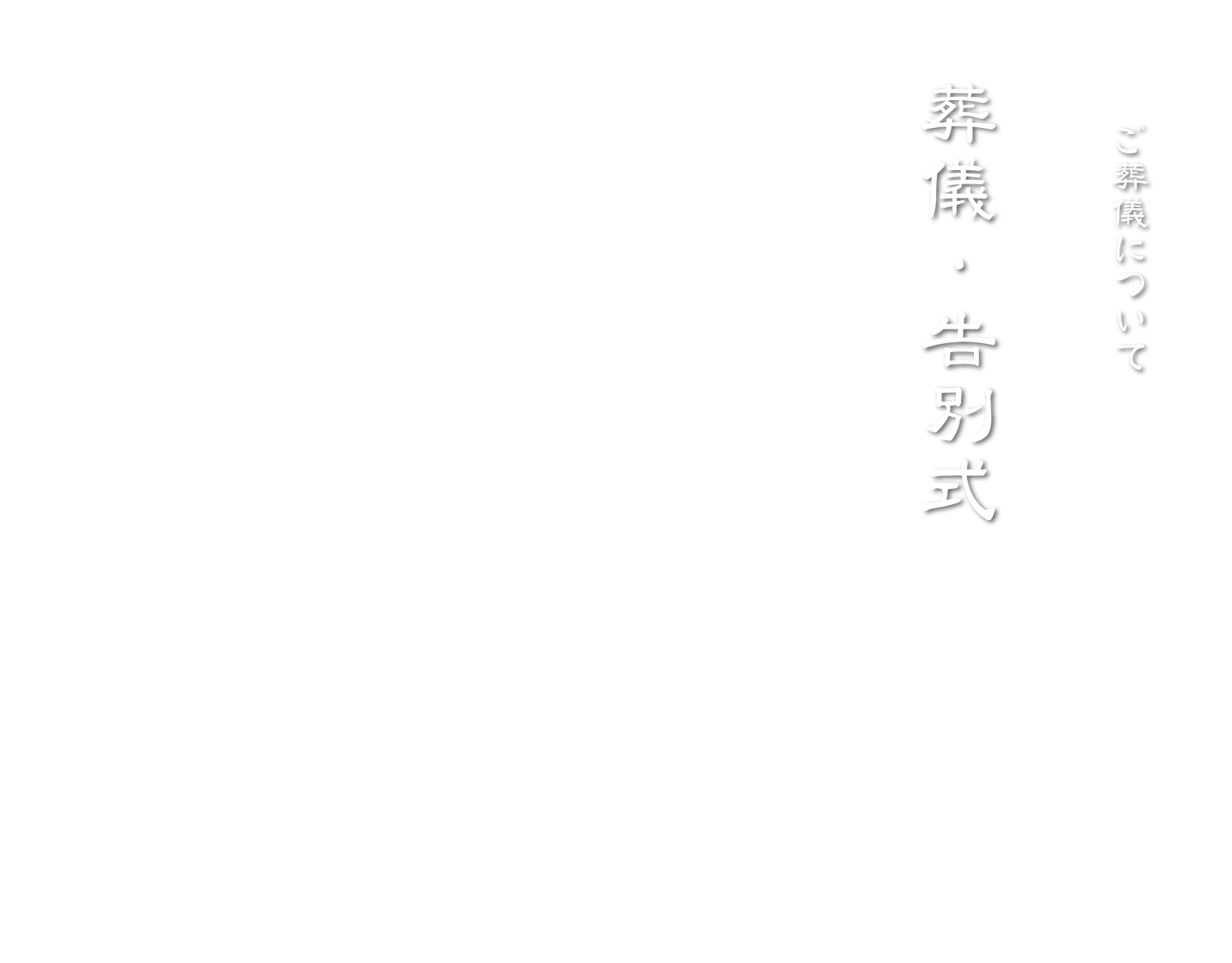
葬儀は遺族・親族が故人のご冥福を祈る儀式であり、告別式は故人の友人、知人、所属の団体、ご近所の方など一般の参列者が故人とお別れをする儀礼です。
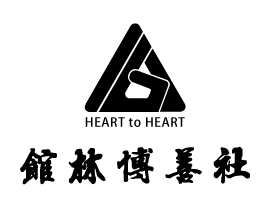

一般的な葬儀・告別式の流れは以下の通りです。
葬儀は遺族・親族が故人のご冥福を祈る儀式であり、告別式は故人の友人、知人、所属の団体、ご近所の方など一般の参列者が故人とお別れをする儀礼です。
ですが、現在では一緒に行うのが一般的になっています。
また、一般の方は仕事の都合などで、お通夜か告別式のどちらかのみに参列することが慣例化してきました。
受付係は葬儀開始時刻の30分前から受付を開始できるよう準備します。
お通夜と同様に、弔問客に挨拶をして香典を受取り、芳名帳に名前・住所・連絡先を記帳してもらいます。
世話役は受付が済んだ弔問客を席へ案内します。
遺族、親族が着席をし、僧侶をお迎えして読経が行われ故人の冥福をお祈りします。
弔辞、弔電が祭壇に供えられた後、遺族・親族が焼香をします。
喪主の挨拶は故人に代わって参列者へ感謝の思いを伝えるものです。
故人と自分との関係、弔問のお礼、生前のご厚意への感謝、故人の人柄がわかる出来事、遺族への今後のお力添えの願いを、およそ長くても3分程度にまとめて挨拶します。
遺族、親族の焼香が済むと、一般の参列者の焼香が行われます。
一般の参列者の焼香が始まった時点から「告別式」となります。
初七日はご逝去されてから7日目に行われる法要ですが、遠方から参列されている方や皆様のご都合を考慮し、また多くの方に故人を偲んでいただけるように、初七日法要を葬儀の際に一緒に行うことを、「繰り上げ初七日法要」といいます。
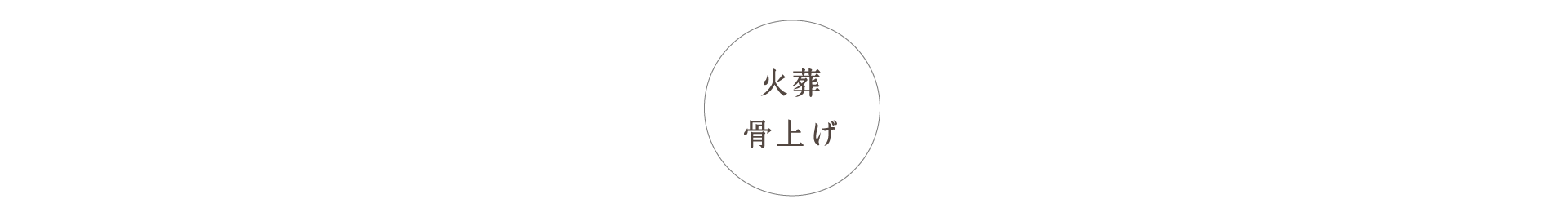
火葬には「火葬許可証」が必要です。
葬儀前に市区町村へ「死亡届」を提出し、
「火葬許可証」を発行してもらいます。
葬儀・告別式の最後に、遺族・親族により故人との最後の対面となる「別れ花」を手向け、石打ちをして棺を閉じます。
法要の後、ご遺体を納めた棺を霊柩車にのせて、火葬場に向けて出棺します。
分骨(二つの墓に納骨する)を希望する場合は「分骨証明書」が必要です。事前に葬儀社にお伝えください。
速やかに火葬場へ移動できるように、遺族、親族、故人のごく親しい方など、火葬場に向かう人数を事前に把握しておきましょう。
通常火葬には1~2時間かかります。
火葬終了まで控室でお待ちいただきます。
火葬が終わると火葬場へ行かれた皆さんで「骨上げ」を行い、骨壺にお骨を納めます。
※骨壺と埋葬許可書は四十九日の法要までご自宅で大切に保管ください。

精進落とし・お斎(おとき)は、収骨後に一同で故人を偲びながら、
僧侶や世話役をはじめ葬儀でお世話になった方々を招き、
労いと感謝の気持ちを込めて食事の場を設けることです。
「後飾り祭壇」は、四十九日の忌明けまで自宅に祭壇をつくり故人の冥福を祈ることです。
祭壇には、宗派によって多少違いがありますが、仏式の一般的な飾りつけは以下のもとなります。

葬儀の一連が終わった後、ご遺族が期限以内にしなければならないことは以下の通りです。
葬儀社から葬儀にかかった費用の請求書が、葬儀終了後から数日以内に届けられます。
見積書や葬儀中に別途かかった出納記録などと確認をし、お支払いください。
その他にも、死亡後1か月以内、1年以内など期限以内に届出・手続きが必要なものがあるのでご注意ください。
菩提寺の僧侶の都合を伺い、死後49日以内に法要が行えるようお勤めを依頼します。
参会者は遺族・近親者のみです。法要後には会食の席を設けます。
納骨の埋葬については、「いつまでにしなければならない」という規定はありませんが、四十九日忌法要後、お墓の準備ができ、ご遺族の気持ちの整理がついた時に納骨供養をしましょう。
回忌法要は、故人の祥月命日(亡くなられた月日)に執り行われる法要のことです。
一回忌から始まり、三回忌、七回忌、十三回忌・・・と年回忌の法要が行われます。
法要を行う日取りはちょうど命日でなくても良いですが、命日を過ぎないようにしましょう。
葬儀は遺族・親族が故人の
ご冥福を祈る儀式であり、
告別式は故人の友人、知人、
所属の団体、ご近所の方など
一般の参列者が故人と
お別れをする儀礼です。


一般的な葬儀・告別式の流れは
以下の通りです。
葬儀は遺族・親族が故人のご冥福を祈る儀式であり、告別式は故人の友人、知人、所属の団体、ご近所の方など一般の参列者が故人とお別れをする儀礼です。
ですが、現在では一緒に行うのが一般的になっています。
また、一般の方は仕事の都合などで、お通夜か告別式のどちらかのみに参列することが慣例化してきました。
受付係は葬儀開始時刻の30分前から受付を開始できるよう準備します。
お通夜と同様に、弔問客に挨拶をして香典を受取り、芳名帳に名前・住所・連絡先を記帳してもらいます。
世話役は受付が済んだ弔問客を席へ案内します。
遺族、親族が着席をし、僧侶をお迎えして読経が行われ故人の冥福をお祈りします。
弔辞、弔電が祭壇に供えられた後、遺族・親族が焼香をします。
喪主の挨拶は故人に代わって参列者へ感謝の思いを伝えるものです。
故人と自分との関係、弔問のお礼、生前のご厚意への感謝、故人の人柄がわかる出来事、遺族への今後のお力添えの願いを、およそ長くても3分程度にまとめて挨拶します。
遺族、親族の焼香が済むと、一般の参列者の焼香が行われます。
一般の参列者の焼香が始まった時点から「告別式」となります。
初七日はご逝去されてから7日目に行われる法要ですが、遠方から参列されている方や皆様のご都合を考慮し、また多くの方に故人を偲んでいただけるように、初七日法要を葬儀の際に一緒に行うことを、「繰り上げ初七日法要」といいます。
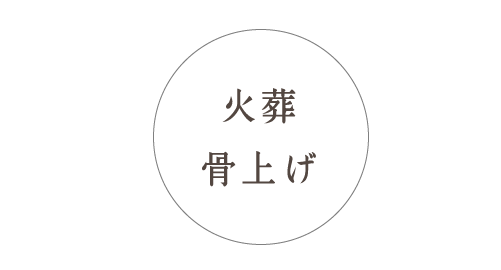
火葬には「火葬許可証」が必要です。
葬儀前に市区町村へ「死亡届」を
提出し、「火葬許可証」を
発行してもらいます。
葬儀・告別式の最後に、遺族・親族により故人との最後の対面となる「別れ花」を手向け、石打ちをして棺を閉じます。
法要の後、ご遺体を納めた棺を霊柩車にのせて、火葬場に向けて出棺します。
分骨(二つの墓に納骨する)を希望する場合は「分骨証明書」が必要です。事前に葬儀社にお伝えください。
速やかに火葬場へ移動できるように、遺族、親族、故人のごく親しい方など、火葬場に向かう人数を事前に把握しておきましょう。
通常火葬には1~2時間かかります。
火葬終了まで控室でお待ちいただきます。
火葬が終わると火葬場へ行かれた皆さんで「骨上げ」を行い、骨壺にお骨を納めます。
※骨壺と埋葬許可書は四十九日の法要までご自宅で大切に保管ください。

精進落とし・お斎(おとき)は、収骨後に一同で故人を偲びながら、
僧侶や世話役をはじめ葬儀でお世話になった方々を招き、
労いと感謝の気持ちを込めて食事の場を設けることです。
「後飾り祭壇」は、四十九日の忌明けまで自宅に祭壇をつくり故人の冥福を祈ることです。
祭壇には、宗派によって多少違いがありますが、仏式の一般的な飾りつけは以下のもとなります。

葬儀の一連が終わった後、
ご遺族が期限以内にしなければならないことは以下の通りです。
葬儀社から葬儀にかかった費用の請求書が、葬儀終了後から数日以内に届けられます。
見積書や葬儀中に別途かかった出納記録などと確認をし、お支払いください。
その他にも、死亡後1か月以内、1年以内など期限以内に届出・手続きが必要なものがあるのでご注意ください。
菩提寺の僧侶の都合を伺い、死後49日以内に法要が行えるようお勤めを依頼します。
参会者は遺族・近親者のみです。法要後には会食の席を設けます。
納骨の埋葬については、「いつまでにしなければならない」という規定はありませんが、四十九日忌法要後、お墓の準備ができ、ご遺族の気持ちの整理がついた時に納骨供養をしましょう。
回忌法要は、故人の祥月命日(亡くなられた月日)に執り行われる法要のことです。
一回忌から始まり、三回忌、七回忌、十三回忌・・・と年回忌の法要が行われます。
法要を行う日取りはちょうど命日でなくても良いですが、命日を過ぎないようにしましょう。